研究で分かった認知症になりやすい性格とは
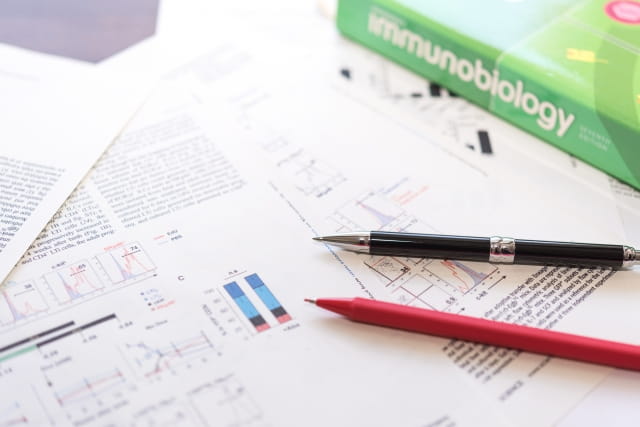
認知症の研究が進んでいるアメリカでは、ニューヨーク州にあるロチェスター大学が、82,232人を54年間にわたって追跡するという非常に大規模な調査を行いました。
対象は15歳から18歳だった若者たち。
彼らが高齢に達するまでの過程を追跡し、どのような人が将来認知症になったのかを統計的に分析したこの研究から、特に注目されたのが「性格的要素」です。
以下の2つの傾向が、特に認知症の発症リスクと関連していることが分かりました。
| 性格的特徴 | 発症リスクとの関係 |
|---|---|
| 責任感が薄い | 高リスク(仕事・家庭で役割を果たさない) |
| 活力(エネルギー)が低い | 高リスク(無気力、やる気がない) |
たとえば、定職に就かず、仕事の責任をすぐ放棄してしまう人や、家庭の中でも父親・母親としての役割をちゃんと果たさない…といった「責任感の薄い人」は認知症になりやすい傾向があったのです。
また、「何をするにもやる気が出ない」「無気力な生活を続けてきた」エネルギーの低い人たちも同様にリスクが高かったとされています。
生活の中で性格によるリスクを減らす方法
では、これらの性格的な傾向に心当たりがある場合、今からでも対策はできるのでしょうか?
答えは「Yes」です。
年齢に関係なく、「日常的に責任を伴う役割を意識し、活力をもって生活すること」は、脳の活性化にもつながります。
具体的な対策例①:役割を持って生活する

たとえば、退職後でも地域のボランティア活動に参加したり、孫の面倒を見る役割をもったりすることで「自分には役割がある」と感じることができます。
この“自分は必要とされている”という感覚は、脳への非常に良い刺激になります。
具体的な対策例②:日常に刺激と楽しみをプラス

もう一つの工夫として、日々の生活にちょっとした「変化」や「挑戦」を取り入れてみましょう。
新しい料理にチャレンジする、散歩コースを変えてみる、習い事を始めるなど、小さなことでも“やる気”や“好奇心”は心に活力を与えます。
無気力な食事や何も考えずに見るテレビばかりの生活では、脳はどんどん受け身になってしまうからです。
心の健康が脳と体を守る鍵になる時代へ
これまで「認知症」と言えば、食事や運動、遺伝、脳血流などが主な原因として重視されてきました。
しかしこの研究結果から、若いうちからの性格傾向、つまり“生き方”が、長年かけて脳に影響を与える可能性があることが科学的に示されています。
特に現在は、定年後に無気力になってしまったり、コロナ禍をきっかけに生活リズムが乱れたりと、多くの人が「活力の低下」を感じている傾向があります。
そんな今だからこそ、心のメンテナンスが認知症予防の大きな一歩となります。
この記事のまとめ
高齢になっても、心を元気に保つことが、自分自身も周囲も笑顔にする第一歩です。
日々の過ごし方次第で、認知症予防は誰にでもできるのです。
※参照:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
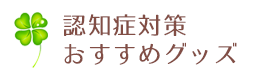





コメント