認知症高齢者の詐欺被害が増加
近年、認知症の高齢者を狙った詐欺被害が増え続けています。
特に、送りつけ詐欺や投資詐欺、リフォーム詐欺などが多発し、家族が気づいたときにはすでに高額のお金を支払ってしまっているケースも少なくありません。
被害者本人が認知症を患っているため、契約の経緯を説明できず、損害賠償を求めることが難しいケースが多発しています。
そこで、今回は認知症の高齢者を守るために家族ができる対策について詳しく解説します。
認知症高齢者が狙われやすい詐欺の手口とは
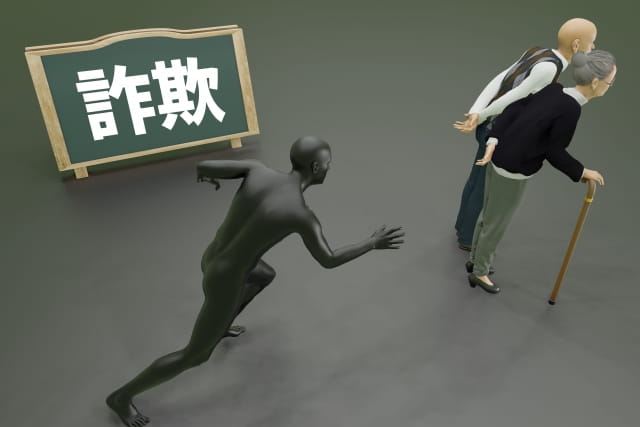
認知症の方は判断力が低下しやすいため、言葉巧みに誘導されてしまうケースが多くあります。
特に被害が多い詐欺のタイプは以下の通りです。
| 詐欺の種類 | 主な手口・被害例 |
|---|---|
| 送りつけ詐欺 | 注文していない商品(健康食品や日用品など)を送りつけ、代金を請求 |
| 架空請求・投資詐欺 | 不要な金融商品や投資話を持ち掛け、高額な契約をさせる |
| リフォーム詐欺 | 不必要な住宅リフォームを契約させ、高額請求する |
| オレオレ詐欺 | 家族を装い緊急性の高い状況を作り、高額な振り込みを要求 |
例えば、ある80代男性は証券会社の営業担当の勧めるまま投資商品を購入し、結果として740万円の損失を出しました。
また、78歳の女性は不要なリフォーム工事を5年にわたって契約させられ、1600万円もの支払いをしてしまいました。
認知症が進行すると「騙された」という自覚を持てないことも多く、家族が気付いたときには被害が広がってしまっていることがほとんどです。
家族ができる詐欺被害の予防策
詐欺の被害に遭わないためには、家族の見守りが重要です。
以下の対策を取ることで、詐欺被害を防ぐことが可能です。
- 電話をチェックする
・迷惑電話対策機能のある電話機を導入する
・家族以外の番号は着信拒否設定にする - 郵便物や契約書を確認する
・定期的に郵便受けをチェックし、不審な通知がないか確認
・高齢者の預金通帳を定期的に確認し、怪しい引き落としがないか注意 - 訪問販売に対応しないよう伝える
・「契約は家族と相談する」と説明してもらう
・訪問販売はすべて断る習慣をつける - 成年後見制度の活用
・認知症の進行が進んでいる場合、家庭裁判所を通じて成年後見人をつける
・これにより、不審な契約を無効にしたり、資産管理をサポートできる

詐欺に遭ったときの対応方法
万が一、詐欺に遭ってしまった場合には、すぐに対応することが大切です。
1. クーリングオフを利用する
・リフォームや訪問販売の契約が成立していても、8日以内であれば解除可能なケースが多い
2. 消費生活センターに相談する
・各地域の消費生活センターに相談することで、詐欺業者への対応策をアドバイスしてもらえる
・【消費者ホットライン:188(いやや!)】へ相談
3. 警察や弁護士に相談する
・明らかに違法な詐欺行為である場合は警察に相談
・民事トラブルである場合、弁護士に対応を依頼
被害を拡大させないためには、家族が迅速に動くことが必要です。
認知症を患う高齢者の方が、安心して暮らせる環境を作るためには、家族のサポートが不可欠です。
日頃から「詐欺の手口」を知り、対策を継続することで大切な家族を守りましょう。
この記事のまとめ
※参考 国民生活センター
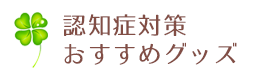





コメント